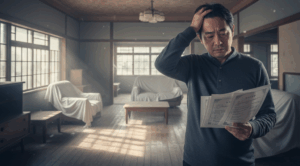
相続登記できない(または相続が困難な)状況でも、空き家をなんとか活用したい!という方のために、「相続ができないときの空き家活用3選」を解説します。法律や制度上問題ない使い方を中心に、安全に進めるためのポイントも含めています。
相続ができないとはどんな状況か
まず「相続ができない」状態がどういうことを指すか確認しておきます。
-
相続人が誰か分からない・所在不明
-
被相続人が誰もいない(相続人不存在)
-
相続放棄をする人ばかりで、誰も所有を引き継がない(ただし管理義務などは残るケースあり)
-
遺言もなく、遺産分割協議ができないなど、所有関係の証明が困難なとき
こういうケースでは、「通常の所有名義人がいない」「所有権を取得できない」ため、登記など法的な手続きを取れない状態です。でも、放置しておくと管理コストや税負担が増えるなどリスクがあるため、何らかの活用を考える価値があります。
空き家活用3選:相続不能時にできる方法
以下は「所有権取得や名義変更ができない/難しいけど、活用できる選択肢」です。
1. 相続財産管理人を選任する
家庭裁判所に申請して相続財産管理人を設けてもらう方法です。所有名義人不明・遺産放棄などで相続人が不在・所在不明の土地・建物の管理をしてもらうことが可能になります。
メリット
-
法的な管理者が決まるため、建物維持や安全確保など最低限の「管理責任」を果たすことができる。
-
管理者が必要な改修や清掃などを行い、近隣トラブルを予防できる。
-
所有権取得に近づける状況を整えられることがある。
デメリット・注意点
-
裁判所手続きが必要で、時間と費用がかかる。
-
管理人の報酬や予納金など、管理コストが発生する。
-
完全な所有権を得られるわけではなく、活用の制限が残ることが多い。
2. 所有者不明土地・建物管理制度を利用する
2023年~施行された新しい制度で、「所有者不明土地・建物管理制度」があります。所有者が分からない土地や建物について、利害関係人が申立てをして管理人を選任し、管理・処分の一部を代行してもらえる制度です。
メリット
-
所有者が明確でなくても管理・処分を進めるルートが法律で整備された。
-
管理人による売却や解体等の措置が認められることもある。
-
利害関係者として(隣地所有者など)申立てできるケースもあり、地域の住民が関与しやすい。
デメリット・注意点
-
申立て・管理人選任等に裁判所運営が関わるため、時間や書類の準備が大変。
-
管理人の報酬・予納金などのコスト負担が発生。
-
制度が対象外となるケース(例えば土地と建物の状態・所有者の所在調査が十分でない等)もある。
3. 国庫帰属制度または公共団体・団体・企業への寄付・売却を検討する
-
不要な土地・建物であれば、国または自治体に帰属させる制度を利用できることがあります。
-
また、公共性のある団体(NPO・公益法人など)に寄付したり、自治体が用いる公共用途として引き取ってもらったりする方法。
メリット
-
維持管理や税金等コストの責任から解放される可能性がある。
-
空き家・土地を地域貢献に使えるケースでは社会的意義も高い。
デメリット・注意点
-
すべての地域・物件が対象になるわけではなく、自治体の政策・条件による。
-
寄付や帰属を受ける側が「場所・状態・権利関係」などを受け入れ可能かの判断が必要。
-
売却より収入が少ない(あるいはゼロ)になる可能性。
法律・制度面での確認ポイント
活用を進める前に、以下の点を必ず確認してください。
-
管理責任・保存義務が誰にあるか(相続放棄しても管理義務は残ることがあります)
-
固定資産税・都市計画税など税負担
-
空家等対策特別措置法における「特定空き家」「管理不全空き家」指定の可能性とその影響
-
所有者不明土地の管理制度が利用可能かどうか・利害関係人として申立てができるか
-
自治体や地域の条例・補助・制度支援があるかどうか
比較:3つの活用方法をどう選ぶか
| 方法 | 費用・手間 | 利益・メリット | 向いているケース |
|---|---|---|---|
| 相続財産管理人 | 裁判所手続き+報酬・予納金 | 管理責任の所在確保・安全維持 | 所有者が不在で誰も管理していない物件 |
| 所有者不明土地管理制度 | 手続き・申立て・管理人関係のコスト | 管理 + 処分の可能性あり | 所有者調査しても不明・利害関係者が関心がある時 |
| 国庫帰属・寄付等 | 合意・自治体の判断等 | コスト負担の軽減・地域貢献 | 売却市場が極端に低い or 利用困難な土地・建物 |
結論:まずは“所有権と管理の明確化”から
相続できない状態の空き家を放置するのは負担だけが膨らむリスクがあります。どの方法を取るにせよ、まずは下記のステップから進めるとスムーズです:
-
所有者の調査をできる範囲で行う(登記簿・固定資産台帳等)
-
管理義務や税金負担がどこにあるかを把握する
-
活用が可能かどうかの現地調査をして、どの選択肢が実際に使えるかを比較する
空き家活用TEAMRへのご案内
所有者が明確でない・相続できない空き家については、判断や手続きが難しいことが多いですが、「眠る資産」を活かす余地は必ずあります。
全国の空き家を価値ある不動産に変える『空き家活用TEAMR』では、次のようなサポートを行っています
-
国庫帰属・公共団体への寄付相談
-
最適な活用プラン(賃貸・売却・地域利用など)の提案
まずは、あなたの空き家の状態や地域・権利関係を教えていただければ、どの方法が実際に実現可能かを一緒に見極めることができます。
